えっ、ローン返済が終わったのに、また毎月天引き!?
10kW以上の大容量太陽光をお持ちの皆さんなら、こんな驚きを感じた方もいるのではないでしょうか。実は私自身、一条工務店の家(屋根一体型12.5kW太陽光)に住むオーナーとして、ローン完済後に売電収入が減る現実に直面し、「なんで!?」とショックを受けました。理由は2022年から始まった「廃棄等費用積立制度」。聞き慣れない制度ですよね。私自身も知らなかった制度だったので、今回この制度の仕組みや家計への影響、そして備えるための対策まで、を調べてみましたのでシェアしたいと思います。
一条の太陽光パネルは屋根一体型なので撤去することもないし、制度の対象外なのでは?などの疑問も浮かぶと思います。私自身、その疑問を持ちモヤモヤしながら制度について調べ始めました。なのでもし同じ戸惑いを抱える方がいらっしゃったら少しでも安心し、将来への準備に繋がれば嬉しいです。一緒にモヤモヤを解消していきましょう!
我が家の一条工務店のスペック
- セゾンA
- 太陽光発電12.5KW搭載
- 2階建て 3LDK
- 建坪 約40坪
- 家の外周にウッドデッキ設置
- 勾配天井
- 4人家族+大型犬一頭(ラブラドールCoco)
- オール電化
一条の太陽光10kw以上オーナーが知るべき廃棄等費用積立制度とは?
「廃棄等費用積立制度」って何?一言でいうと、将来の太陽光パネル撤去・処分費用を確実に積み立てておくための仕組みです。国の再エネ特措法改正によって2022年7月から導入され、10kW以上の太陽光発電設備すべて(FIT※やFIP認定案件)が対象になりました。つまり、一条工務店か他社かに関係なく、10kW以上の太陽光パネルを載せている家庭は基本みんな当てはまります(「ウチは住宅用だから関係ないよね?」と思われがちですが、10kW以上は法律上“事業用”扱いなので対象なんです)。
仕組みはとてもシンプル。太陽光発電の売電収入から毎月一定額が自動的に差し引かれ、国が指定する外部機関に積み立てられます。差し引かれる金額は発電量に応じて決まり、太陽光の発電事業者(私たちオーナー)は手元に入る売電収入がその分減ることになります。積立が始まるタイミングは「FIT売電期間が終了する10年前から」。多くの事業用太陽光(10kW以上)はFIT期間が20年なので、運転開始から11年目~20年目までの10年間が積立期間となります。例えば2013年7月に売電開始したシステムなら、2023年7月から積立開始です。
では毎月いくら積み立てられるのか?実はこれは設備の認定年度やFIT単価によって細かく決められていて、太陽光の買い取り価格に廃棄費用相当額があらかじめ織り込まれているんです。以下は一例ですが、FIT単価ごとの積立単価(1kWhあたり)の目安をまとめました。
| 認定年度 | FIT買取価格 (税込) | 積立単価 (税込) | 売電収入に占める割合(約) |
|---|---|---|---|
| 2012年度 | 40円/kWh | 1.62円/kWh | 4.0% |
| 2013年度 | 36円/kWh | 1.40円/kWh | 3.9% |
| 2014年度 | 32円/kWh | 1.28円/kWh | 4.0% |
| 2015年度 | 29~27円/kWh | 1.25円/kWh | 4.3~4.6% |
| 2016年度 | 24円/kWh | 1.09円/kWh | 4.5% |
| 2017年度 | 21円/kWh | 0.99円/kWh | 4.7% |
| 2018年度 | 18円/kWh | 0.80円/kWh | 4.4% |
| 2019年度 | 14円/kWh | 0.66円/kWh | 4.7% |
ご覧のように、売電単価の約3~5%前後が毎月の積立に回るイメージです(認定時期によっては6%近くになるケースもあり)。この制度、実は前々から任意で積み立てること自体はFITの認定条件に含まれていました。しかし国の調査では、事業者ベースで計画的に積み立てていたのはたった16%に過ぎなかったそうです。将来、撤去費用が用意できず放置・不法投棄されるリスクを減らすため、強制的に源泉徴収する形(外部積立)で積立金を確保する制度が作られた、という背景があります。
なお、一部の大規模発電所に限り例外的に自分で積み立てる「内部積立」も認められていますが、50kW以上など厳しい条件があるため(金融機関の監査を受ける等)、私たち家庭オーナーのほとんどは関係ナシ。基本は電力会社が毎月の売電代から自動天引きする外部積立になります。
一条の太陽光10kw以上オーナーはショック!ローン完済なのにまた天引き!?
よし、太陽光ローン払い終わった!来月から売電収入まるまる家計のプラスだ!・・・と思った矢先に、新たな天引きが始まる――これは心理的に結構ショックですよね。私も10年払いのパネルローンを完済したタイミングで来年から積立分が引かれると知った時は「なんで今さらお金取られるの!?」と声が出ました。
実際のところ、この減収の正体は先述の積立制度によるものです。つまり「ローン→積立」と払先が置き換わっただけで、毎月の手取りが減ったわけではない…と言いたいところですが、やっぱり一旦自分の懐に入るはずのお金が減るのはショックですよね。特に制度を知らなければ、「完済後は月◯万円浮くはず!」と期待していた分、なおさら落胆してしまいます。
天引き額は平均で売電収入の3〜5%ほどですが、長年の運用を頑張ってきたオーナーからすると「ご褒美期間」に水を差される感覚になるかもしれません。でも積立金は言わば本当に無くなるお金ではなく、将来の撤去費用として自分に戻ってくる可能性が高いんです(申請方法は後述)。知らないと損した気分ですが、知れば味方にできる制度とも言えます。
📝豆知識:売電明細の見方…積立開始後の売電明細には、「解体等積立金」などの項目でその月の控除額が表示されます。(地域や電力会社によって表示名称は異なる場合があります)。
ただここで屋根一体型太陽光パネルを採用している一条オーナーにとって、1つ疑問が浮かびませんか?そうです。一条の場合、太陽光パネルは屋根一体型なので、もし太陽光として機能しなくなっても屋根としてそのまま使い続ける場合、撤去しないので撤去費用の積立はする必要ないのでは?(廃棄等費用積立制度の対象外では?)ということです。
私もまさにこれについて疑問に思いました。ただ将来、家を取り壊したり、パネルを取り替えたりする場合は撤去することになるので、その時の撤去費用ということのようです。
確かにそう言われると間違いではないのですが、例えば家を取り壊すときに自分がまだ生きているの?みたいな疑問は浮かびますよね。この辺りは後述しますが、自分たちの子供や親族に積立があることをしっかりと引き継いでおかないといけないようです。
一条の太陽光10kw以上だと実際の積立額はいくら?シミュレーションで確認
ある程度、廃棄等費用積立制度の内容を知ったところで、次は具体的に家計にどう響くのかをシミュレーションしてみましょう!
実際に積立が始まると、毎月どのくらい手取り収入が減るのか気になりますよね。ここでは具体例にどれだけ積立て売電価格が減るのかシミュレーションしてみます。
▼ケース例:10kWシステム(FIT単価27円/kWh)の場合
- 年間発電量:約10,000kWh(地域や環境によりますが、10kWなら年1万kWh前後は発電するイメージです)
- 月間発電量:約833kWh(年間を12で平均した仮の値)
- 月間売電収入(積立控除前):833kWh × 27円= 22,491円
- 積立控除額(月):833kWh × 1.25円 = 1,041円※積立単価1.25円/kWhはFIT27円の場合
- 月間売電収入(積立控除後):21,450円(約4.6%ダウン)
ざっくり毎月1,000円前後が天引きされる計算です。このケースでは年間にすると約1.25万円、10年間では累計12.5万円が積み立てられる見込みとなります。実はこの12.5万円という額、国が想定する10kW設備の標準的な廃棄費用にほぼ相当します(※後述の撤去費用相場もご参照ください)。つまり「20年後に必要なお金」を逆算し、発電量に応じて10年間で貯めるイメージですね。
とはいえ1,000円/月の減収は小さくないですよね。例えば我が家ではローン返済月額が約2万円だったので、完済後は+2万の余裕が生まれる!と期待していました。それが実際は+1.9万円ほど(そこからさらに税金等もありますが😅)。予定より毎月1千円少ないと聞くと地味に残念…。ですが、逆に言えば毎月たった1千円の負担で、将来15~30万円とも言われる廃棄費用を備えられるとも考えられます。このあたり、捉え方ひとつで気持ちも変わりますね。
シミュレーションしてみて、「思ったより大した額じゃないかな?」と感じた方も、「やっぱり痛い…」と感じた方もいるでしょう。次章では、「そもそも自分は積立なんて関係ないのでは?」という誤解ポイントを整理します。実は対象者全員に関係大アリなので、ここでしっかり確認してくださいね👍
一条の太陽光10kw以上オーナーが気になる廃棄等費用積立制度に関するFAQ
積立制度について調べ始めると、よく聞くのが「ウチは屋根一体型の太陽光パネルで発電しなくなっても屋根として使うつもりだから、撤去費なんて積み立て不要では?」という声。お気持ちは分かりますが…この制度、たとえ“撤去しない派”でも完全には無関係でいられません!ここでは勘違いしやすいポイントをQ&A形式で整理します。
Q1.「将来パネル撤去しないなら、お金取られるだけ損?」
A1.いいえ、将来ずっと撤去しなくても“損”にはなりません。積立金は最終的に撤去等を行う時まで推進機関に預けておく形になります。例えばFIT終了後も自家消費や新たな売電先でパネルを使い続ける方も多いでしょう。その場合、積立金は国にプールされたままで、撤去やリプレースを行うタイミングで申請して返金を受け取れます。つまり、「使わないまま消える」ことは基本的になく、太陽光パネルを撤去するときまで“キープ”されるんです。ただし、取り戻すには所定の手続きが必要なので「知らずに放置」だけはしないようにしましょう(申請方法は後述)。
Q2.「住宅用だから対象外でしょ?」
A2.“10kW以上なら”家庭でも対象です!この点が紛らわしいところですが、法律上10kW以上=事業用とみなされ、一律で積立対象になります。実際、一条工務店など大容量パネルを載せる住宅も増えていますが、そのオーナーも例外ではありません(私もそうでした…)。逆に10kW未満のご家庭(いわゆる余剰買取の住宅用)は対象外なので、例えば一条オーナーでも搭載量が8kWなら積立制度は関係ありません。要はパネル容量10kWを境に制度の有無が分かれるので、「自分はどっち?」を確認しておきましょう。
Q3.「自分で積み立てちゃダメなの?銀行に貯金しておくから放っておいて!」
A3.基本的にNGです(ごく一部の大規模事業者のみ可能)。国も当初は「各自で積立ててね~」と自主性に任せていましたが、前述の通りほとんど実行されなかったため強制徴収に踏み切った経緯があります。私たち小規模オーナーは制度に従うしかありません。「内部積立」を選べるのは50kW以上・法人など特殊な条件を満たす場合のみで、しかも事前に経産省への相談・承認が必要です。現実問題、個人宅レベルでは内部積立は選択肢に入らないと考えた方がいいでしょう。
Q4.「パネルは壊れるまで置いておけばいい。撤去費なんて払わず放置もアリ?」
A4.放置はおすすめしません。太陽光パネルは寿命こそ20~30年と長いですが、いずれ必ず廃棄の時が来ます。寿命を迎え大幅に発電しなくなったパネルを屋根に載せ続けてもメリットは乏しく、むしろ雨漏りや落下リスクも出てくるかもしれません。そのため最終的には適切な撤去・処分が義務となります。積立金が戻るのもちゃんと処分した場合だけなので、せっかく貯めたお金を活かすためにも放置は得策ではありません。「いつかは処分する」という前提で計画しておくのが、結局は安心ですよ。
モヤモヤが解けたでしょうか?要するに「積立制度は10kW以上ならどんなオーナーにも基本関係あり」「積立金は将来必ず役立つから無駄ではない」ということですね。では次に、その大切な積立金をちゃんと把握する方法をお伝えします!
以下は資源エネルギー庁の廃棄等費用積立制度に関するFAQページです。最新の情報はこちらで確認するようにしましょう。
太陽光パネル廃棄等費用積立残高を“見える化”する3ステップ
「積立」とはいっても、実際には国の機関にプールされているだけなので、自分の手元では見えにくいお金です。でも折角コツコツ貯まっているなら、今いくら貯まってる?と気になりますよね。ここでは、オーナー自身が積立残高を把握するための3つのステップを紹介します。
●Step1:毎月の売電明細をチェック
まずは電力会社からの「再生可能エネルギー受給電力量のお知らせ」(売電明細)を確認しましょう。積立開始後の明細には、売電量・売電金額とともに「解体等積立金」などの名目で控除額が記載されています。例えば中部電力ミライズの場合、明細の欄に「積立金〇〇円」とはっきり表示されます。この毎月の積立控除額を把握するのが第一歩です。紙の明細書は捨てずにファイリングしておきましょう(Web明細の方はスクショやPDF保存がおすすめ)。
●Step2:積立額を累計して記録
次に、毎月の控除額を累計してみましょう。地道な方法ですが、私の場合はエクセルに「月ごとの積立額」を入力して合計を計算しています。例えば年間で1万円積み立てられるなら、5年間で約5万円…と自分で貯金残高を確認するイメージですね。特に発電量は年々変動・減少しますから、毎年の積立額も多少増減します。年単位くらいで「今年は○○円積み立てられた」とメモしておくと、将来必要額との対比もしやすいですよ。
●Step3:公式システムで残高を確認(必要なら登録)
「自分で計算するのは不安…」という方は、国の公式システムでも積立残高を確認できます。その場合は電力広域的運営推進機関(OCCTO)のWEBシステムにオーナー情報を登録する必要があります。登録手続きは少々手間ですが、認定事業者(オーナー本人)として氏名・住所・設備IDなどを申請すると、承認後にオンラインで自分の積立状況が閲覧可能になります。なお、このシステムは認定事業者本人しか登録できないので、ご家族に代理してもらう場合は注意してください。以下に電力広域的運営推進機関のホームページのリンクを貼っておきますね。
以上のステップで、「自分の積立はいま◯◯円」と把握できるようになります。見えないお金も見える化すれば愛着(?)が湧くもの。「お、順調に○万円貯まってるぞ」と分かれば、将来への備えとして前向きに捉えられますよね。
では、積立金をしっかり把握できたところで、「じゃあ不足しないようにするには?」という視点でオーナーができる3つの対策を考えてみましょう!
太陽光パネル廃棄等費用積立の不足を防ぐ対策3選~将来に備えるために~
「積立不足」とは、将来パネルを廃棄する際に必要な費用 > 積立金となってしまう状態です。できれば避けたいですよね。国の積立基準額も完璧ではないので、オーナー側でも備えを万全にしておきましょう。ここでは積立不足を防ぐ3つの対策を紹介します。
対策1:発電量をキープ!設備メンテナンスで積立額アップ
積立金は発電した分だけ貯まる仕組みです。つまり、発電量をできるだけ落とさないようにすることが、そのまま積立金不足防止につながります。太陽光パネルは年々劣化しますが、年0.5%程度の出力低下に抑えられるのが一般的です。しかしホコリや鳥のフン、周囲の草木の成長による影などで、本来より多く発電ロスしてしまうことも…。定期的な点検・清掃でパネルの発電効率を維持し、発電ロスを未然に防ぐことが大切です。一条工務店の場合、モニタリングサービスで異常を検知してくれる仕組みもあります。パワーコンディショナの故障放置などで長期間発電できないと、その間積立も貯まりません。異常を早期発見・修理してダウンタイムを最小限にしましょう。要は「発電=積立」なので、設備をベストコンディションに保つことが積立アップの鍵です。まー、自分で別建てで積み立ててもいいんですけどね。
対策2:不足分は自前で貯蓄!廃棄費用を試算し計画的に積み増し
国が想定する積立額は標準的なケースに基づいていますが、実際の廃棄費用はケースバイケースです。例えば我が家のような屋根一体型パネルの場合、パネル撤去後に屋根材の補修や張り替えが必要になる可能性があります。この屋根修復費用は状況によって10万~100万円と大きく変動し得ます。また3階建てなら高所作業で足場代が嵩んだり、前面道路が狭ければ誘導員など追加費用も発生します。一般的な5kW家庭用でも撤去費用は25~40万円が相場と言われますが、それは足場代等を含まない最低ラインです。実際に一条オーナーの方が取った見積もりでは、総額108万円(!!)というケースもあったとか。
こうしたことを踏まえると、「積立金+α」を自前で用意しておくのが安心です。具体的には、積立金で賄えない差額分を見積もって、今から少しずつ貯蓄しておくこと。例えば「撤去費用はうちの場合50万円くらい?」と予測したら、積立で賄えそうな20万円との差額30万円を20年かけて積み増すイメージです。毎月にすれば1,250円程度のプラス貯金で済みますよね。売電収入の一部をさらに手元貯金に回しても良いですし、蓄電池やリフォームなど将来の投資計画に組み込んで備えてもOK。ポイントは「積立金だけに過信せず、念のため余裕を持っておく」ことです。まー、そもそも電力を売電したお金で家計の足しにしようと思っているのに、そこまで撤去費用のことを考えないといけないなんて、本末転倒だー、なんて思いたくなっちゃいますよね。。
対策3:タイミングが大事!撤去計画と住宅メンテを連携
将来の撤去タイミングを賢く計画することで、費用負担を減らせる可能性があります。例えば屋根の塗装や補修を検討しているなら、太陽光の撤去と同時期に行うことで足場設置費用を二重に払わずに済みます。20年前後でパワコン交換や屋根メンテナンスの時期も来るでしょうから、太陽光の撤去・更新と住宅メンテをセットで計画すると効率的です。一条工務店オーナーの場合、高耐久の屋根材が使われていますが、それでも将来パネルを降ろす際には何らかの処置が必要になるかもしれません。そのタイミングで新しい太陽光パネルに載せ替える選択肢もあります。実は積立金はパネル交換の場合にも有効活用でき、古いパネルの処分費用に充てて残りは引き続き運用…という形も可能です。いずれにせよ、自分の家のライフサイクル全体を見据えて「いつ撤去するのがベストか」を検討しておくと、無駄な出費を抑えつつ積立金を最大限活かせます。計画的な撤去=計画的な資金準備です。5年後・10年後…と定期的に見直しながら、「最もコスパ良く撤去できるタイミング」を見極めていきましょう。
以上、積立不足を防ぐための3つの対策をご紹介しました。発電量の維持と資金計画、そして計画的な撤去の段取りで、「足りない!😱」を「ちょうど足りた👌」にしていきましょう!
申請漏れゼロを実現する“家族引き継ぎマニュアル”のススメ
積立金を無事に貯めても、最後に取り戻す手続きを忘れてしまっては元も子もありません…!特に太陽光のFIT終了~撤去時期というのは20年も先の話。オーナー自身が高齢になっていたり、場合によっては代替わりしている可能性もあります。そこでぜひ作っておきたいのが、積立金に関する「家族引き継ぎマニュアル」です。
🔑マニュアルに盛り込みたいポイント
- ① 基本情報の整理 …太陽光発電設備の認定番号やFIT契約の期間(開始年月日と終了年月日)を明記しておきます。例えば「20XX年○月FIT終了、同年から積立開始、積立期間は○年間」など。一条工務店の書類や経産省の認定通知に記載がありますので写しておきましょう。
- ② 積立金の概要説明 …家族向けに「○○という制度で、これまでに△万円積み立てられている。このお金は太陽光パネルを撤去するときに受け取れる」と簡単に説明文を書いておきます。「知らない人にはチンプンカンプン」ですから、平易な言葉でポイントを書くのがコツです。
- ③ 払い戻し申請の手順 …積立金を受け取るための手続きをステップごとに記載します。例えば「1. パネル撤去工事を業者に依頼」「2. 工事契約書と見積書を保管」「3. OCCTO(推進機関)に申請書提出」といった具合です。実際の手続きでは、撤去前に申請する場合と撤去後に申請する場合で必要書類が異なります。解体前申請なら業者との契約書・費用明細書、解体後申請なら契約書に加え産業廃棄物管理票(マニフェスト)や工事写真・領収書などが必要です。こうした書類も「必ず取っておくこと」とマニュアルに書き添えてください。
- ④ 連絡先リスト …いざという時に相談・問い合わせできるよう、関係先の連絡先も載せておきます。例として、OCCTO積立金担当窓口、契約中の電力会社(売電先)のお客様番号と電話、太陽光を設置した工務店やメーカーの連絡先など。特に推進機関(OCCTO)は積立金管理者なので、申請方法等の問い合わせ先として明記しておきましょう。後述の「問い合わせ先ガイド」も参考にしてください。
- ⑤ 認定事業者の承継方法 …万一オーナー本人が亡くなった場合など、太陽光発電の認定事業者を承継(名義変更)する必要があります。この手続きをしないと、家族が積立金を受け取れなくなる恐れがあります。ですので、「相続時には経産省への承継届出をすること」もマニュアルに記載します。具体的な方法(オンラインシステムでの申請等)はその時点で確認してもらうとして、「名義変更を忘れずに!」という注意喚起が肝心です。
- ⑥ その他 …太陽光設備の保証書やメンテナンス記録、FIT契約書なども一緒にファイルしておくと親切です。つまり太陽光に関する一切の書類・情報をまとめたバインダーを用意し、「◯◯(家族名)宛:太陽光積立金マニュアル在中」とでも書いて保管しておくイメージです。
このマニュアルがあれば、仮にオーナー本人が対応できなくても家族が代わりにしっかり申請を行い、積立金を取り戻すことができます。「そんな先のこと、まだいいや」ではなく、思い立った今がチャンスです。私も先日マニュアルを作成し、妻に内容を共有しておきました。「20年後かぁ、私たち何歳だ?」なんて笑い話もしつつ😂、でも家族に安心を引き継ぐ大事な準備だと実感しています。
ただ実際の一条の太陽光10kw以上のオーナーとしては何度も言いますが、屋根一体型のパネルの場合、ほとんどのオーナーが生前に撤去はないと思いますので、生きている間に積立金が受け取れるようにしてくれないと結構な確率で積立損になってしまうと思います。
かといって何か良い案があるわけではないのですが新しい制度を考える人は不平等にならないように制度設計して欲しいなと思います。
もしもの時の問い合わせ先ガイド
最後に、積立制度や太陽光撤去について困ったときの相談先をご紹介します。いざという時に連絡先が分からないと不安ですから、ここで確認しておきましょう。
- 💼経済産業省 資源エネルギー庁(国の公式情報)
制度の概要や最新情報を知りたいときは、まず資源エネルギー庁のWebサイトをチェックしましょう。公式発表資料やQ\&A、ガイドラインPDFが公開されています。「太陽光発電廃棄費用積立制度 資源エネルギー庁」などで検索すると該当ページが見つかります。電話での問い合わせ窓口もエネ庁にありますので、制度そのものの疑問は国に直接聞くのもアリです。 - 🏢電力広域的運営推進機関(OCCTO)
積立金の管理主体であるOCCTO(オクト)は、積立金残高の確認や払戻申請に関する実務窓口です。WEB上にはFAQや申請様式、システム登録の案内等が掲載されています。問い合わせはメールフォームが基本ですが、FAQに載っていない個別ケース(例えば承継手続きの詳細など)は電話相談も可能です。OCCTOのサイト内「再エネ関係の方→問い合わせ」から連絡できます。 - 🔌ご契約の電力会社(売電先)
毎月の積立控除額のことで疑問があれば、契約中の電力会社に問い合わせましょう。各電力会社の再エネ買取担当窓口で対応してもらえます。例えば中部電力ミライズでは公式サイトに積立制度のページがあり、概要や問い合わせ先が案内されています。東京電力パワーグリッドでも同様に情報提供があります。「明細に積立金が載っていない」「控除額が計算と違う気がする」などの疑問は、まず電力会社に確認するとスムーズです。 - 🏠一条工務店・施工業者
一条工務店など住宅メーカーや太陽光施工業者も、顧客向けに情報提供や相談に乗ってくれる場合があります。特にパネル撤去を依頼する際は、施工元に相談すれば見積もりや手順のアドバイスが得られるでしょう。将来、撤去や載せ替え工事を検討する際には、まず信頼できる業者に問い合わせてください(その際、積立金の存在も伝えると話が早いです)。 - ♻️廃棄・リサイクル関連団体
太陽光パネルのリサイクル推進団体や自治体の環境課なども相談先になります。大量廃棄時代に備えてガイドラインが整備されつつあり、各地で相談窓口を設ける動きがあります。「太陽光パネル処分○○市」などで検索すると地元の情報が得られるかもしれません。将来的に補助金制度が出る可能性もあるので、自治体情報は定期的にチェックすると良いでしょう。
こうした窓口を活用しながら、不明点は遠慮なく質問してみてください。20年という長いスパンの制度ですから、疑問はそのままにせず都度解消しておくことが大切です。私も最初はチンプンカンプンでしたが、中部電力さんやOCCTOに問い合わせて一つひとつ理解を深めました。その結果、今では「もし○○になったら…」というシミュレーションまでできるように。皆さんもぜひ頼れるものは頼って、万全の備えをしていきましょう😉。
一条の太陽光10kw以上オーナーが知るべき廃棄等費用積立制度まとめ
長文お付き合いいただきありがとうございました。それでは最後に、本記事の内容をチェックリスト形式で振り返りましょう!💡
- ☑ 自分の太陽光は積立制度の対象?
→ 10kW以上なら対象。FIT期間終了の10年前から売電収入の一部が控除されます。該当する方は以下チェックを! - ☑ 積立金の月額・年間額を把握した?
→ 毎月控除される額はFIT単価の約3~5%相当。自分の契約では月いくら引かれるか計算し、家計プランを調整しておきましょう。 - ☑ 売電明細を確認&記録している?
→ 明細書に積立控除額が記載されています。毎月チェックし、できれば累計をエクセル等で記録。積立残高の“見える化”を! - ☑ 発電設備のメンテナンス計画は万全?
→ パネル清掃やパワコン点検で発電ロスを減らし、積立額も最大化。故障を放置しないよう、メーカーのモニタリングサービス等を活用しましょう。 - ☑ 将来の撤去費用を試算した?
→ 我が家の場合いくらかかりそうか、大まかにシミュレーション。差額が出そうなら別途貯蓄計画を!自治体補助や新技術動向もチェックです。 - ☑ 撤去のタイミング戦略は考えてある?
→ FIT後すぐ外す?それともパネル交換して延命?住宅メンテと合わせて実施?ベストなタイミングを家族と話し合っておきましょう。 - ☑ 家族への引き継ぎ準備はOK?
→ 「太陽光積立金マニュアル」を作成し、万一の時に備えて家族と共有。承継手続きや申請書類リストも忘れずに。 - ☑ 困ったときの相談先は把握済み?
→ 国(資源エネ庁)、OCCTO、電力会社、施工業者など頼れる窓口をメモ。不安なことはプロに相談してクリアに!
チェックはいかがでしたか?一つでも「まだ💦」があれば、これを機に対応を進めてみてください。廃棄等費用の積立制度は最初こそ驚きますが、理解すれば私たちオーナーと社会の将来にちゃんと備えるための心強い制度だと分かります。私も知識ゼロからスタートしましたが、今では「これで20年後も怖くないぞ」と前向きな気持ちです。皆さんもぜひ、本記事を参考に安心の太陽光ライフを続けてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。疑問や体験談があれば、ぜひコメントで教えてください!お互い情報交換しながら、一条オーナー仲間として賢くエコライフを満喫しましょう😉👍



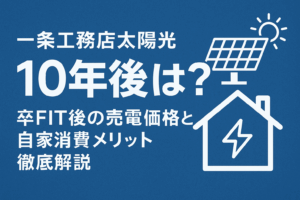
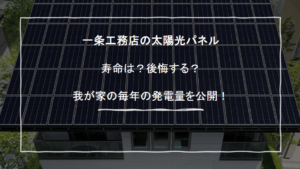


コメント