一条工務店の住宅に10kW以上の大容量太陽光発電システム「夢発電システム」を搭載されたオーナーにとって、その投資が20年後、そしてそれ以降も持続的な価値を生み出し続けるかという問いは、極めて重要な関心事でしょう。
私自身、一条工務店の家に住み、10kW以上の大容量太陽光発電を使っているのでその気持ちは本当に分かります。
そこで本記事では、一条工務店の太陽光発電システムが持つ独自の強みから、FIT期間満了後の経済性、長期運用におけるメンテナンス、そして将来に向けた賢い選択肢まで、自分自身でも調べまとめてみました。少しでも将来計画のプラスになれば幸いです。
我が家の一条工務店のスペック
- セゾンA
- 太陽光発電12.5KW搭載
- 2階建て 3LDK
- 建坪 約40坪
- 家の外周にウッドデッキ設置
- 勾配天井
- 4人家族+大型犬一頭(ラブラドールCoco)
- オール電化
一条工務店の太陽光発電、20年後どうなっていますか?
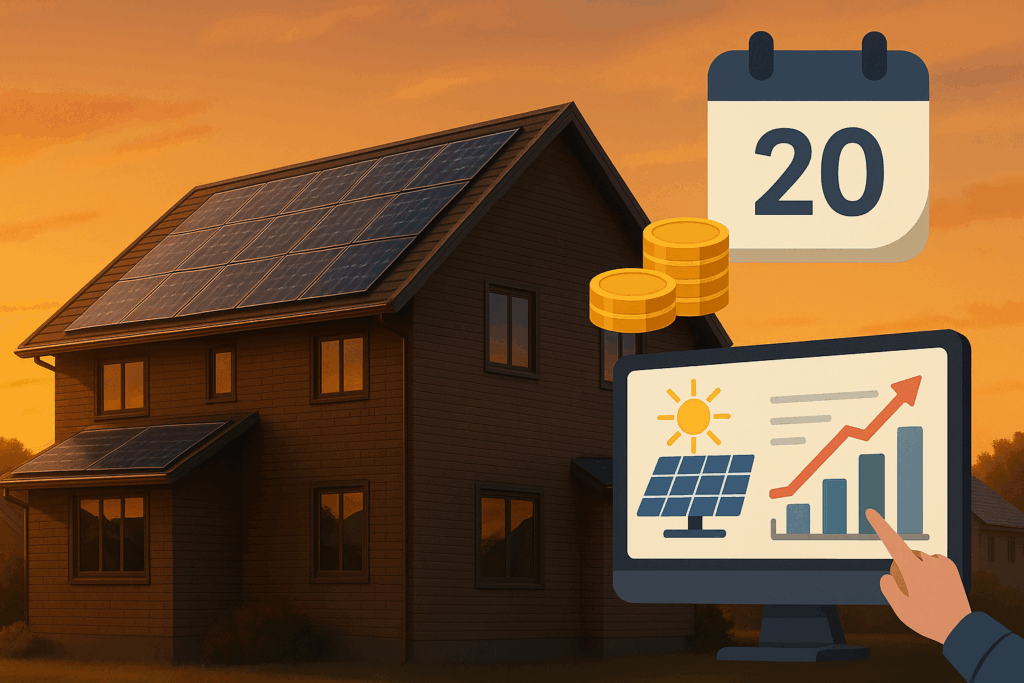
10kW以上システムオーナーが直面する現実
固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーの普及を目的とし、国が定めた固定価格で電力を買い取ることを電力会社に義務付ける制度です。特に2012年には、10kW以上の太陽光発電システムに対する全量買取制度が始まり、その認知度が飛躍的に向上しました。10kW以上の太陽光発電システムは、売電期間が20年間と設定されており、これは10kW未満の住宅用太陽光発電の売電期間が10年間であることと比較すると倍の長さであり、長期にわたる安定した売電収入を期待できる点が大きなメリットでした。
しかし、一条工務店の太陽光パネルのメーカー保証期間は10年間とされており、これはJIS基準の最低保証期間です。太陽光パネル自体の耐用年数は20年と想定されているため、この10年間の保証期間と耐用年数の間に「保証のギャップ」が生じます。つまり、10年目以降の故障は原則として有償修理となることを意味します。この保証のギャップは、10年目以降の故障リスクをオーナー自身が負うことを意味しますが、一条工務店はモニタリングシステムを通じてお客様宅の太陽光発電システムの稼働状況を定期的に確認し、不具合を検知した際には点検・修理の手配を行うサービスを提供しており、安心感につながります。
初期投資の回収期間については、一条工務店の発電払いプランで約12年半という試算があり、これによりFIT期間の残り7年半で約170万円の経済的メリットが見込まれるとされています。また、別の試算では、10kW以上の容量を設置した場合、約10年を超える運用期間で設置費用が償還できるとされています。ちなみに我が家は9年11カ月で償還することができました。
発電量と収益の変化をチェック
太陽光パネルは、時間の経過とともに太陽電池セルの劣化などにより発電効率が徐々に低下します。一般的には、年間約0.5%程度の出力低下が目安とされています。この劣化率に基づくと、20年後には新品時の約80%~90%程度の発電効率を維持できると予測されます。多くの太陽光パネルメーカーは、この経年劣化を考慮し、「20年後も初期の80%以上の出力を保証」といった出力保証を設定しています。太陽光パネル自体の耐用年数が法定耐用年数(17年)よりも長く、25~30年稼働が見込まれていることも考慮すべきです。
一条工務店の発電シミュレーションは、しばしば保守的な数値で提示される傾向があります。あるオーナーの10.5kWシステムでは、年間予想発電量9,088kWhに対し、実際の年間発電量は2018年に10,801kWh、2019年に11,417kWh、2020年に11,211kWh、2021年に11,021kWh、2022年に10,716kWhと、いずれもシミュレーション値を大きく上回る実績を残しています。この実例では、シミュレーション比で110%~165%という高い発電効率を記録しており、一条工務店の屋根一体型パネルによる広範囲な設置面積と、高断熱住宅による効率的な電力消費が相乗効果を生み出し、実際の発電量を押し上げている可能性を示唆しています。
ちなみに我が家の発電量の実績は以下の記事にまとめてあります。
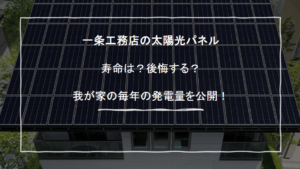
一条工務店の太陽光発電の20年後、売電はもう「稼ぐ」手段じゃない?
新たな売電価格の現実と買取先の選び方
FIT期間満了、通称「卒FIT」とは、固定価格での電力買取期間が終了することを指します。10kW以上の太陽光発電システムの場合、導入から20年後にこの期間が終了します。卒FIT後、電力会社は固定価格で電気を買い取る義務がなくなり、買取価格はFIT期間中と比べて大幅に下がるのが一般的です。現在の卒FIT買取価格は、大手電力会社や新電力会社によって異なりますが、概ね7円~15円/kWh程度が相場です。中には蓄電池導入を条件に20円/kWhといった高単価で買い取る限定的なプランも存在します。
売電価格が下がるため、卒FIT後は売電を継続するよりも「自家消費」に切り替える方が経済的なメリットが大きくなる傾向にあります。これは、電力会社から電気を買う価格(例えば東京電力の従量電灯Bで約25円/kWh)と、卒FIT後の売電価格に大きな差があるため、「自家消費」による電気代削減効果が売電収入を上回るためです。この状況は、太陽光発電で自家消費する電気のコストが、電力会社から購入する電気のコストよりも安くなる「グリッドパリティ」が起こっていることを示しています。卒FIT後の買取価格は、電力会社や地域によって大きく異なるため、最も有利な買取プランを提供する新電力会社への切り替えを積極的に検討すべきです。
これからは自家消費が「賢い選択」になる理由
昨今の電気料金高騰は、自家消費の経済的メリットをさらに顕著にしています。国際情勢や円安の影響で電気代が家計を圧迫する中、自家消費は効率的なコスト削減策として注目されています。自家消費型太陽光発電の最大のメリットは、電気代の削減です。余剰買取方式と比較して、電気使用量を直接削減しやすく、その分電気代削減効果を伸ばしやすいと言えます。
自家消費は、環境負荷低減(CO2削減)やエネルギー自給率向上にも貢献します。火力発電由来の電力消費を減らし、非常時の電源確保にも役立ちます。この変化は、太陽光発電の役割が「売電による収益化」から「電気代削減による家計防衛とエネルギー自給率向上」へと根本的に変化したことを示しており、今後の住宅におけるエネルギー戦略の主流となるでしょう。
蓄電池導入で電気代を劇的に削減する方法
太陽光発電単体では、夜間や悪天候時の電力供給に限界があります。しかし、蓄電池を導入することで、日中に発電した余剰電力を貯めておき、夜間や早朝、あるいは電気料金が高い時間帯に利用することが可能になります。これにより、電力会社からの購入を最小限に抑え、自家消費率を大幅に向上させ、電気代削減効果を最大化できます。
一条工務店は、蓄電池導入を支援するサービスも提供しており、高出力・大容量のオリジナル蓄電池「エネパワボL」などがあります。「エネパワボL」は9.8kWhの大容量で、エアコンやIH調理器などの200V機器にも対応し、停電時も家中のコンセントが使える「全負荷型」である点が特徴です。蓄電池やV2Hシステムを導入することで、発電した電力を貯蔵し、必要な時に利用できるため、電力会社からの購入を最小限に抑え、エネルギー自給自足に近づくことができます。これは、単なる経済的メリットを超え、国際情勢やエネルギー価格の変動に左右されない「安心感」をもたらします。
ただし我が家のように現在蓄電池がない場合、蓄電池を後付けする必要があります。ここに落とし穴がって、以前調べた結果ですと蓄電池の後付けは事実上難しいとのことです。というのも蓄電池を後付けすることで現状の設備が変わってしまうため電力の買取価格が現在の単価に変更になってしまうとのこと。
これだとかなり減額になるので事実上、蓄電池の後付けは難しいという調査結果でした。ただこれは現時点の運用なので設備が変わっても買取価格を維持する運用にしてくれれば蓄電池を後付けできることになります。なので個人的には早く運用が変わり、蓄電池の後付けができるようにしてほしいと思っています。詳しくは以下の記事にまとめてあります。

ただし蓄電池が後付けできるとしたら、複数の製品やサービスを比較検討することが重要です。たとえ後付けできなくても現状の蓄電池の相場を知っておくことは今後の備えとして大切です。そんな時、便利なのが蓄電池比較サイトのエコ×エネです。複数の施工会社から相見積もりを取ることができ、独自の審査基準で悪質業者を排除し、優良企業のみを紹介しているため、安心して利用できます。強引な営業がないよう特定商取引法を厳守し、コンプライアンス部門が厳しくチェックしている点も信頼できます。
V2H導入でEVが「動く蓄電池」に変わる?
V2H(Vehicle to Home)システムを導入すれば、電気自動車(EV)を「走る蓄電池」として活用できます。太陽光発電で得た電力をEVに蓄え、家庭用電力として逆流させることで、さらなる自家消費率向上と電気代削減が期待できます。EVのバッテリー容量は家庭用蓄電池よりも圧倒的に大容量であり、節電効果や非常用電源としての有用性が非常に高いです。
一条にもV2Hがあってこれを後付けできれば電気自動車の電池を蓄電池として活用できます。そもそも一条のV2Hが後付けできるかどうかまで調べ切れていないのですが、そもそもその前に一条のV2HはEVから家庭への給電は停電発生時に限定されており、通常時には車から家へ電気を送ることはできません。なので太陽光で発電した電力をEVにためるのみとなります。
一般的に他社のV2HはEVと家庭の電力を双方向でやり取りできるので、そうなると他社のV2Hを後付けしたくなりますよね。そこまで調べ切れていないので徐々に調べていこうと思っています。V2Hについては以下の記事にまとめてあります。

一条工務店の20年経った太陽光パネルとパワコンの寿命は?
パネルの劣化状況と発電効率のリアル
太陽光パネルは、紫外線や風雨にさらされることで徐々に劣化し、発電効率が低下します。一般的には年間約0.5%程度の出力低下が目安とされており、この劣化率に基づくと、20年後には新品時の約80%~90%程度の発電効率を維持できると予測されます。多くのメーカーは「20年後も初期の80%以上の出力を保証」といった出力保証を設定しており、これは長期的な発電量の期待値を設定する役割を担っています。太陽光パネル自体の耐用年数は25~30年と、法定耐用年数(17年)よりも長く稼働が見込まれています。
パワーコンディショナー交換は必須?費用とタイミング
パワーコンディショナー(パワコン)は、太陽光発電システムが発電した直流電力を家庭で使える交流電力に変換する、システムの「心臓部」です。その耐用年数は約10年~15年と太陽光パネルよりも短いため、20年間の運用期間中に1回は交換が必要となる可能性が非常に高いです。
パワコンの交換費用は、機器本体価格と工事費を含めて30万円~40万円が一般的な相場です。ただし、メーカーや機器の容量、設置環境によって異なり、シャープ製の場合は60万円~70万円、三菱製は約40万円~50万円が目安となることもあります。経済産業省のデータでは平均値約22.4万円とされていますが、これはあくまで平均であり、個別のケースでは変動幅が大きいことを理解しておくべきです。交換工事費は、家庭用の5.5kWパワコン1台あたり約9万円前後が目安で、これに電力会社や経済産業省への申請などの事務手数料として約1万円前後が必要となります。
私自身、7年目にパワコンが故障しました。ただ10年の保証期間でしたので無償交換でした。詳しくは以下の記事に書いてあります。

パワコンの交換は、故障してからではなく、寿命を迎える前に計画的に行うことが推奨されます。機器によっては納期が数ヶ月かかる場合があり、故障による売電収入のロスを避けるためです。また、新しいモデルのパワコンは技術進歩により変換効率が飛躍的に向上しており、古いパワコンを新しいものに交換するだけでも数%程度の発電量増加が見込めます。このリパワリングは、単なる故障修理ではなく、発電効率の向上やメンテナンスコストの削減といった明確な経済的リターンが見込める「戦略的投資」と言えます。
配線、意外と見落としがちな部品の劣化
太陽光発電システムは、パネルやパワコンだけでなく、配線、分電盤、売電メーターなど、様々な部品で構成されています。これらの部品も経年劣化や外部要因により損傷する可能性があります。
- 配線・ケーブル類:太陽光パネルの裏側にはケーブルが配線されており、施工不良や経年劣化、雑草などによる外部からの影響で損傷することがあります。配線が劣化したり断線したりすると、電気が正しく流れなくなり、発電量減少や火災の原因となる恐れがあります。定期的な点検で異常を早期に発見し、必要に応じて交換することが大切です。
- 分電盤・売電メーター:これらも長期運用で交換が必要となる部品です。例えば、分電盤は20年ごとに3万円、売電メーターは15年ごとに2万円が目安とされています。
これらの費用は個々には大きくなくても、積算すると数十万円規模になるため、初期投資回収後の収益計画に大きな影響を与えます。これらを事前に把握し、売電収入の一部を計画的に積み立てておくことで、突発的な出費に慌てることなく、安定した長期運用が可能になります。
一条工務店オーナーが知るべき屋根一体型パネルの特殊性
一条工務店の屋根一体型太陽光パネルは、屋根材としての認定を受けているため、一般的なスレート屋根のように塗り直しが不要であり、高い耐久性を持っています。これにより、屋根自体のメンテナンスコストが削減されるメリットがあります。また、外観の美しさを保ちながら、屋根面積を最大限に活用し、発電量を最大化できるという機能的なメリットも両立しています。
しかし、屋根一体型であるため、パネルの故障や交換が必要になった場合、通常の屋根置き型よりも作業が複雑になり、費用が高くなる可能性があります。パネル1枚あたりの交換費用は3万円~5万円程度が相場とされています。一方で、屋根一体型は部品点数が少なく構造がシンプルなため、メンテナンスは従来タイプと同等かやや簡単になるという見方もあります。
「メンテナンスフリー」と言われることもありますが、これは屋根材としての塗装不要を指すものであり、太陽光発電システムとしての定期点検や部品交換は必須です。特に一条工務店は自社グループ生産で独自のパネルを使用しているため、専門的な知識と技術を持つ一条工務店のアフターサービスへの依存度が高いと言えます。精密な点検や専門的な知識が必要となるため、一条工務店のアフターサービスや専門業者への依頼が不可欠です。
一条工務店の太陽光発電の20年目のメンテナンスと今後のコスト

無償保証終了後のメンテナンス計画
一条工務店の太陽光パネルのメーカー保証期間は10年間とされています。この保証期間が終了した後も、システムの安定稼働を維持するためには計画的なメンテナンスが不可欠です。一条工務店はモニタリングシステムを通じてお客様宅の太陽光発電システムの稼働状況を定期的に確認し、不具合を検知した際には点検・修理の手配を行うサービスを提供しています。これにより、オーナーが発電状況を常に気にすることなく、専門家が「見守ってくれている」という安心感を得られます。
我が家も前述した7年目にパワコンが故障した際に、一条工務店が太陽光システムの運用を委託しているダイヤゼブラ電機から電話があり、故障に気付け、発電ロスを最小限に抑えられたことがありました。
想定外の故障発生!修理費用の目安と備え
太陽光パネル1枚あたりの交換費用は3万円~5万円程度が相場とされています。
屋根上での作業には足場が必要となることが多く、2階建て住宅で7万円~10万円程度が目安です。足場代は高額であり、点検のたびに発生すると費用負担が大きくなります。この費用を効率化するためには、太陽光発電のメンテナンスと屋根の葺き替えや外壁塗装など、住宅本体のメンテナンスを同時に行う「統合的アプローチ」が有効です。これにより、足場設置の回数を減らし、総コストを抑えることができます。
大規模修繕(リパワリング)は本当に必要?
リパワリングとは、既存の太陽光発電システムの主要部品、特にパワーコンディショナー(パワコン)を交換・アップグレードすることで、発電量を改善し、収益を増加させる戦略です。パワコンは技術進歩により変換効率が飛躍的に向上しており、古いパワコンを新しいものに交換するだけでも数%程度の発電量増加が見込めます。
リパワリングは、FIT期間中であっても検討の価値があります。特に、設備の劣化で発電量が落ちている場合に効果が高く、早い段階で実施することでメンテナンスコストの削減や新たなメーカー保証の適用といったメリットも得られます。リパワリングは単なる故障修理ではなく、発電効率の向上やメンテナンスコストの削減といった明確な経済的リターンが見込める「戦略的投資」です。特にFIT期間中に実施すれば、高い売電価格で発電量増加の恩恵を享受でき、投資回収を早めることが可能です。リパワリングは一度にまとめて行う方が、工事費用が安くなる、メーカー保証に入りやすい、パワコンの故障による売電ロスがない、といった費用対効果が高いとされています。
災害保険と太陽光発電:20年後の見直しポイント
太陽光発電設備は屋外に設置されるため、火災、落雷、風災、雪災、盗難などの自然災害や事故による損害リスクに常に晒されています。これらのリスクに備えるため、適切な災害保険への加入が重要です。
近年、火災保険や休業損害補償の保険料が大きく値上がりしています。2024年10月には、火災保険料が約2倍に、休業損害補償(発電不能による収入損失を補償)に至っては約6倍に値上げが実施されました。また、免責金額(自己負担額)も上がっており、例えば100万円を下回る損害は補償されないケースや、設備工事費用の10%が免責金額となるケースもあります。
20年後を見据え、保険契約を見直す際には以下の点に注意が必要です。
- 補償範囲の確認:太陽光発電設備が現在加入している火災保険や企業総合保険の補償範囲に含まれているか、自然災害への補償が適切かを確認しましょう。必要に応じて補償範囲の拡大を検討します。
- 免責金額の確認:自己負担額がいくらになるのかを把握し、万が一の際に備えておきましょう。
- 保険料と補償内容のバランス:保険料が高騰している現状を踏まえ、必要な補償に絞ることで保険料を抑えることも可能です。
- 定期的な見直し:太陽光発電システムの長期運用においては、保険会社と定期的に相談し、適切な契約を維持することが重要です。
メーカー保証は、製造上の不備や経年劣化による出力低下を補償するものですが、自然災害による損害は対象外となることが多いため、別途災害保険で備える必要があります。
一条工務店の太陽光発電の税金や法規制、20年後の注意点

固定資産税は払い続けるべき?
発電設備は「償却資産」と見なされ、法定耐用年数である17年にわたって固定資産税が課税されるのが原則です。しかし、課税標準額が150万円を下回ると、その年度以降は固定資産税が免除されます。これは、多くの家庭用太陽光発電システムでは、17年を待たずに数年で固定資産税の課税が終了する可能性が高いことを意味します。
初期費用600万円のシステムの場合、税制優遇措置を適用すると、1年目の固定資産税は約5.2万円、3年目で約4万円となり、この例では6年目から納税義務がなくなる試算もあります。また、「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」により、課税評価額が最初の3年間は1/2または2/3に軽減される場合があります。ただし、この特例はFIT認定を受けている設備は対象外となるケースもあるため、個別の状況を確認することが重要です。
太陽光パネル廃棄にかかる費用と将来の義務
前述の通り、2022年7月から、10kW以上の太陽光発電事業者に対して、廃棄費用の積立が義務化されました。これは、将来の環境負荷を軽減し、持続可能な社会に貢献するための重要な制度であり、FIT期間終了後のシステムの「出口戦略」の一部として組み込まれています。
積立は、FIT制度を導入している10kW以上のすべての太陽光発電設備が対象となり、売電収入から自動的に差し引かれます。積立が開始されるのは「FITの調達期間が終わる日の10年前から」です。積立基準額はFIT認定年度や容量によって変動しますが、売電収入の約4%~6%程度が廃棄費用として天引きされることになります。
これについては私は知らなかったのですが、我々、一条工務店の10kW以上の太陽光発電を導入している人も対象なのかどうかは要確認です。
まとめ:20年後の太陽光発電、後悔しないためのロードマップ
一条工務店の太陽光発電システムは、20年後も、そしてそれ以降も、オーナーの暮らしに大きな価値をもたらし続ける可能性を秘めています。その価値を最大限に引き出すためには、以下の点が重要となります。
まず、FIT期間満了後の運用を早期に検討し、計画的に実行することが不可欠です。売電価格が低下する卒FIT後は、自家消費へのシフトが経済的な最適解となります。蓄電池やV2Hシステムの導入を検討し、日中の余剰電力を効率的に活用することで、電気代削減効果を最大化し、エネルギー自給自足に近づくことができます。
次に、一条工務店の提供するモニタリングサービスを最大限に活用し、システムの異常を早期に検知し、適切なメンテナンスを継続することが、長期的な発電効率維持の鍵となります。パワーコンディショナーの交換など、避けられないメンテナンス費用は計画的に積み立て、故障による発電ロスを未然に防ぐことが重要です。
さらに、住宅本体のメンテナンス計画と太陽光発電システムのメンテナンスを連携させ、効率的な長期管理を目指しましょう。足場代などのコストを抑えつつ、住宅と設備の双方を最適な状態に保つことができます。
最後に、国の補助金制度や自治体の助成金(例えば、東京都の太陽光発電システム設置義務化に伴う助成金など)は、今後も変動する可能性があります。最新情報を常にチェックし、活用できる制度がないか確認することが、経済的メリットを最大化する上で重要です。一条工務店のオーナーは、手厚いサポート体制と高性能な住宅という強みを活かし、能動的に長期運用に関わることで、20年後も「後悔しない」持続可能で豊かな暮らしを実現できるでしょう。



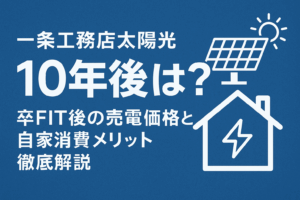

コメント